渋谷らくごプレビュー&レビュー
2016年 12月9日(金)~13日(火)
開場=開演30分前 / *浪曲 **講談 / 出演者は予告なく変わることがあります。


アーカイブ
- 2024年08月
- 2024年07月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年03月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年02月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
- 2021年05月
- 2021年04月
- 2021年03月
- 2021年02月
- 2021年01月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年09月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年02月
- 2019年01月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年07月
- 2018年06月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
プレビュー
◎トークゲスト:春日太一(映画史・時代劇研究家)
落語立川流が生んだバグ こしら師匠の爆笑落語。
今年多忙の一年を疾走した浪曲界の爆笑王子 玉川太福さん。
創作落語で抜群の爆笑精度を誇る百栄師匠。
トリはこの三人をも飲み込むかもしれない魔王の登場です。お楽しみに!
▽立川こしら たてかわ こしら
21歳で入門、芸歴20年目、2012年12月真打昇進。
自称イケメン落語家。HPで写真素材をダウンロードできる。日本中で落語会を開いているが、来年は規模を拡大してシドニーをはじめとした海外での落語会を開く。ポケモンGOを遊び尽くし、ラプラスを捕まえにしっかり東北へ足をのばす。
▽玉川太福 たまがわ だいふく
1979年8月2日、新潟県新潟市出身、2007年3月入門、2012年日本浪曲協会理事に就任。
「わかりやすい浪曲」を目指して日々奮闘中。大学までラグビーを続けていた熱血漢。2015年「渋谷らくご創作らくご大賞」を受賞している。DVDを発売中。
▽春風亭百栄 しゅんぷうてい ももえ
年を取らない妖精のような存在です。静岡県静岡市出身、2008年9月真打ち昇進。
不思議な風貌で、危ないネタをかけつづている。次郎長とさくらももこ先生と昇太師匠とおなじ地元。
アメリカで寿司職人のバイトをしたことがある。猫が大変お好きという意外は日常生活の様子を見せない。
▽お楽しみゲスト
レビュー
12月12日(月)20時~22時「渋谷らくご」
立川こしら(たてかわ こしら)「短命」
玉川太福/伊丹明(たまがわ だいふく/いたみ あきら)「上野掛け取り動物園」
春風亭百栄(しゅんぷうてい ももえ)「天使と悪魔」
笑福亭鶴瓶(しょうふくてい つるべ)「青木先生」
「ワルプルギスの夜」
立川こしらさん
-

立川こしら師匠
アニメ「サウスパーク」のような、安心して苦笑できる大人のエンターテインメントでした。
番組冒頭は、いつものように「実写パート」で、なぜかカウボーイの格好をした作者が登場し、「こんなアニメよく見るよね。月曜の夜から、どれだけ暇なんだい?」と、いきなり「メタ語り」で、とんでもないことを言ってきます。その後も「綾小路きみまろ」みたいな調子で、「今日のスペシャルゲストを知らないだって?君たち『情弱』なんじゃないのかい」などと、近年なかなかテレビじゃお目にかかれない「客いじり」が続いた後、なし崩し的にオープニングが流れて、本編がスタートします。
しかし、その本編も筋らしい筋はなく、いつものように雪深い田舎の学校を舞台に、ただスタンたちが世間話をしているだけなのですが、今回のネタは「担任のギャリソン先生の恋人になる人は、どうしてみんなすぐに死んでしまうのだろう?」というものでした。
そこで、「前回は線の細い美男子だったから、わからなくもないけど、今回は筋骨隆々のマッチョだったのになんでだろう?」と、カイルが不思議そうに言うと、カートマンが「毎回、HIVで死ぬよな!」と、一番言ってはならない結論を、さらっと言ってのけます。
こうした感じで、時には子供であること、時には無邪気であることを隠れ蓑に、好き勝手なことを言っているんだなとゲラゲラ笑いながら見ていると、肝心の大人であるはずのギャリソン先生までもが、あろうことか女装して登場し、パペット人形のハット君に腹話術で、「こいつら馬鹿だよね。白人以外の血が流れてるんじゃないでしょうか?」などと、ドナルド・トランプみたいなヤバイことを言って、こちらに同意を求めてきたりするので、もう滅茶苦茶でした。
このように、「キッズアニメ風の世界観」という、この作品で言えば「古典落語の大枠」は残したままで、それ以外は時事ネタから下ネタに至るまで、縦横無尽に出たり入ったりするという、大変アドリブ性の強い作品に仕上がっていました。もちろん、ケニーは今回も「致死量のご飯」を食べて、お腹が破裂して死んでしまいます。
音楽なら「Beastie Boys」、映画なら「博士の異常な愛情」など、実力に裏打ちされたブラックユーモアと破壊的なギャグが好きな方に、是非とも生で見ていただきたいライブ作品です。
玉川太福さんと伊丹明さん
-

玉川太福さんと伊丹明師匠
明るい「THE DOORS」の「THE END」みたいな浪曲でした。
ジム・モリソンのような、語りとも朗読ともつかない歌声に、ふいに絶妙なタイミングで三味線の音がシャラシャラと絡みつき、サイケデリック・ロックにしては、ひたすらクールな印象のまま、養豚場から逃げ出した豚の物語が「神話風」に語られます。
ですが今作は、一般的な「動物擬人化もの」ではなく、どちらかと言えば「人間動物化もの」といった不思議な世界観を持った作品で、しかも「動物であることの必然性」というのが、必ずしも無いのが大変興味深いところです。
この、動物であり同時に人間でもあるという主人公の「豚」の男が、「上野動物園」に売り飛ばされてしまうところから、物語は始まるのですが、そこで出会った貧しい「アライグマ」の親子を守るために、この動物園を牛耳っている「パンダ親分」と対決するという、手に汗握る男のバトルが繰り広げられます。
そして、クライマックスに、「自分の尻尾」を自らの手で引きちぎって、啖呵を切るという場面を迎えるのですが、ここで演奏もピークに差し掛かります。映画「地獄の黙示録」で言えば、牛の首が切り落とされて、主人公が沼からぬっと顔を出す、丁度あの辺でしょうか。
そして、尻尾のない「新たな動物たちの王」になったこの男が、動物園の住民が次々に頭を下げるなかを通り過ぎ、人間と動物がともに幸せになれる「約束の地」を探して、千葉県へと旅立ったところで、今回は幕が下ろされました。
私が本作を見て特に面白いと思ったのは、「尻尾が無いと、どの動物園にも入れてもらえない」という台詞があるところです。これはどういうことかと言うと、「尻尾」というものが「動物としてのアイデンティティーを象徴するもの」として、描かれているということです。そして、それを自ら捨ててしまうということは、言い換えると、「一度すべてを投げ捨てて、新しい世界へ踏み出していく」ということを意味しています。だからこそ、動物としての自分を当たり前だと思っていた、パンダ親分は降参してしまったのですね。
しかし、ここでひとつ大きな疑問が浮かび上がります。
では果たして今作において、「人間としてのアイデンティティーを象徴するもの」とは、一体何なのでしょうか?
私はこの辺りに、あえて「人間動物化もの」にした、制作者の狙いがあるのではないかと考えています。
他にも映画なら「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」、または「もののけ姫」が好きな方にオススメです。
春風亭百栄さん
-

春風亭百栄師匠
アニメ「惡の華」みたいな、とある落語家の自閉的な苦しみを描いた「暗黒ポエム」でした。
群馬県桐生市を舞台にした本作では、鬱屈した毎日を送っている「高校生落語家」の春日が、次の高座で何をやるべきか、昔から自分にとっての「天使」だった、佐伯さんという憧れの女の子に相談を持ちかけます。すると、保守的な家庭に育った彼女は、「古典落語をやって、昔からの落語ファンを喜ばせたらどうかな?」と、手堅いアドバイスをしてくれます。
思い切って話しかけたことで、意外にも彼女との進展もあり、喜んでいた春日でしたが、ある日クラスメイトで一番の問題児である仲村さんという女性に、「私さ、あんたが佐伯さんの体操着盗むの見てたんだよね」と、一時の気の迷いでやってしまった過ちを、目撃していたことを告白され、それ以降彼女に付きまとわれてしまいます。そして、「あんた、私と契約しなよ。あんたみたいな変態のゴミクズはさ、次の高座で新作落語をかけて、何もかもぶち壊しにしてしまいなよ」と、聞いてもいないアドバイスをしてくるようになります。普通ならピンチに陥るはずの場面ですが、そこは元から屈折しているこの主人公。次第にこの「悪魔」の囁きに耳を貸しはじめ、「・・・そうだね。どうせこんなくだらない世の中、全部滅茶苦茶にしてしまえばいいんだよね」と、段々とその気になってきます。
かくして、表向きは「天使」と清純なデートを重ねて、無難に日々をしのいで行こうとする一方で、そのすぐ裏側では、「悪魔」に自分のドロドロとした欲求不満をぶちまけて、何もかも台無しにしてしまえとそそのかされるという、相反する「天使と悪魔」の囁きによって、主人公の精神は次第に真っ二に引き裂かれて行きます。
そして、とある休日に「盗んだ佐伯さんの体操着を服の下に着て、近所の公園でその本人と初デートをする」という、極めて変態的なことをしている最中に、どこかに隠れていた仲村さんから、バケツ一杯の水を思いっきり頭から突然ぶっかけられるという「意味不明の仕打ち」を受けるに至って、ついに彼は発狂してしまい、「あのクソムシたちを、俺の新作落語でみな殺しにしてやるんだー!」という、わけのわからないことを空に向かって絶叫します。
ことここに至ってみれば、もはや「天使」というものも、ずいぶんと弱気で偽善的な存在だったということ、また「悪魔」というものも、同期で売れている人への、ただの嫉妬から来る欲求不満の当てこすりだったことが判明します。つまりはどちらも、ただの「現実逃避」に過ぎなかったんですね。
結局、次の高座で最終的にどちらをやるのか結論が出ないまま、この作品は終わってしまいますが、私の予想では話の流れからして、十中八九主人公は本番で、「新作落語」を掛けるだろうと思っています。
小説なら「ライ麦畑でつかまえて」、音楽なら「RADIOHEAD」、時代劇研究家なら「春日太一」が好きな方にオススメです。
笑福亭鶴瓶さん
-

笑福亭鶴瓶師匠
テレビ「鶴瓶の家族に乾杯」を、落語に翻訳し直したような文学作品でした。
マイルス・デイヴィスが、「練習とは祈りのようなものである」と言っていますが、この方の落語もどこまでが「芸」であり、どこまでが「素」なのかという「境界」を見極めることが、私には全くできませんでした。
最初、何やら高座に座卓のようなものが置かれるのをみて、「講談か何かをやるのだろうか?」と思っていたのですが、ステージの背後に「笑福亭鶴瓶」という文字が写って、本人が登場したときには、あまりの事に度肝を抜かれ、会場にどよめきが走りました。
しかし、開口一番、「最近、私は足を骨折しましてね。しばらく立ったままで、すんません」と、話しはじめられたとたんに動揺がぴたりと静まり、「え、大丈夫なのかな?」と、会場の空気が一瞬にしてそちらに持って行かれ、ふと気がついてみると、まるで自宅で「きらきらアフロ」でも見ているような、安心感に包まれていたことには本当に驚きました。
やはりこの方は、「人の懐に入る」ということに関しては、まず間違いなく日本で1、2を争う天才だと感じた瞬間です。 そんな「鶴瓶バイブス」を、後光のように放出しまくっている状況のなかで、最近テレビの収録中にあった「面白裏話」や、自分の私生活で起きた「変な出来事」を、公私の区別なく満遍なく次々に語るものですから、ますます彼に対する親密度と、面白い雰囲気の「気圧」のようなものが、どんどんと高まっていきました。
そして、それが頂点に達したころに、これまでの話を一つに抽象化したような「青木先生」という、自分の学生時代にいた、話し方が特徴的な初老の先生と、それにちょっかいを出す生徒との微笑ましいやりとりを落語に仕立て直した、徹底的に練り込まれた本編が始まったため、「ただ楽譜通りに演奏しているにもかかわらず、まるでフリージャズでも聞いているかのような、もの凄いスイング感」が、会場中にほとばしっていました。
そんな案配なものですから、青木先生という名もない老教師の話が、まるで「偉人の逸話」ですらあるかのような輝きを放ち初め、もはや何を言っても爆笑できる「確変」が起きているのを感じるのと同時に、それが自分の思い出や経験ともどんどん共鳴しはじめ、終盤では、もの凄い感動の洪水が心に溢れ出て来ました。
これは間違いなく本物の芸術ですし、文学作品のひとつです。
小説だと「保坂和志」、ラジオなら「東京ポッド許可局」の「忘れ得ぬ人々」のコーナー、アニメなら「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」、映画なら「ニュー・シネマ・パラダイス」が好きな方にオススメです。
以上、一番手はトークゲストで来ていらした時代劇研究家の春日太一さん(この方のお仕事のご縁で、鶴瓶さんの出演が決まったとのことです)が仰るところの、ムショ帰りを意味する『島戻り』が、口八丁でなんでもかんでも売りさばいてサヴァイヴしてしまう、現代のフーテンの寅さんによるバナナのたたき売り。
二番手は『勘定方』、つまり真面目な「事務職」の方に、試しに楽器を持たせてみたら、とんでもないぶっ飛んだ演奏を始めてしまうという、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」みたいな本当にあった夢物語。
三番手は『忍者』、つまりは一番使い勝手のいい順番の「殺し屋」で、目的のためなら自分の命すらためらいもなく捨ててしまえるという、一番ヤバイ類のサタニストが語る「落語信仰」の告白。
そして、ラストは『大殿様』。もはやロビン・ウィリアムズみたいに、悪代官も正義漢もリバーシブルに、そのまんま表現できるほどの高みに達した、「伝説の魔王」が舞う「奇跡の敦盛」でした。
これらの方々の作品には、どれもそれぞれの表現の裏に、うっすらと「面白さに対する、果てしない欲求と渇望」があり、それを落語や浪曲を通して、無意識にこちらに訴えかけてくるのですが、もはやその「我」が強すぎて、ついには核分裂して消滅してしまったかのような、純粋なただの「白熱」を全身で感じていると、マキタスポーツが歌うところの「芸人は人間じゃない」という歌詞の意味が、ようやくわかったような気がしました。
この「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」と言った感じの、悪魔たちによる楽しい楽しい闇夜のサバト。二時間心が躍りっぱなしでした。関係者の方々、とりわけ自ら出演をかって出て下さったという笑福亭鶴瓶師匠に、心から感謝を捧げます。 どうもありがとうございました。
-
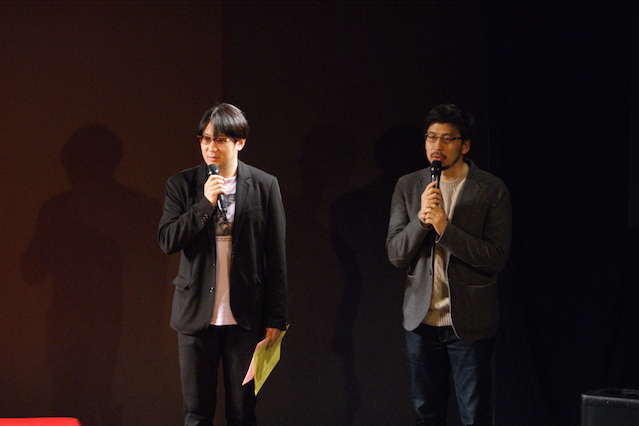
トークゲスト・春日太一さんと
【この日のほかのお客様の感想】
「渋谷らくご」12/12 公演 感想まとめ
写真:渋谷らくごスタッフ
